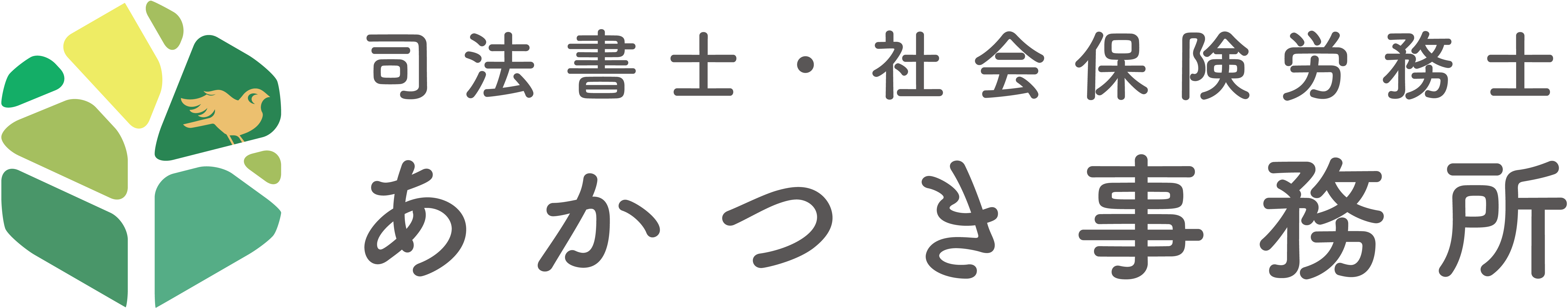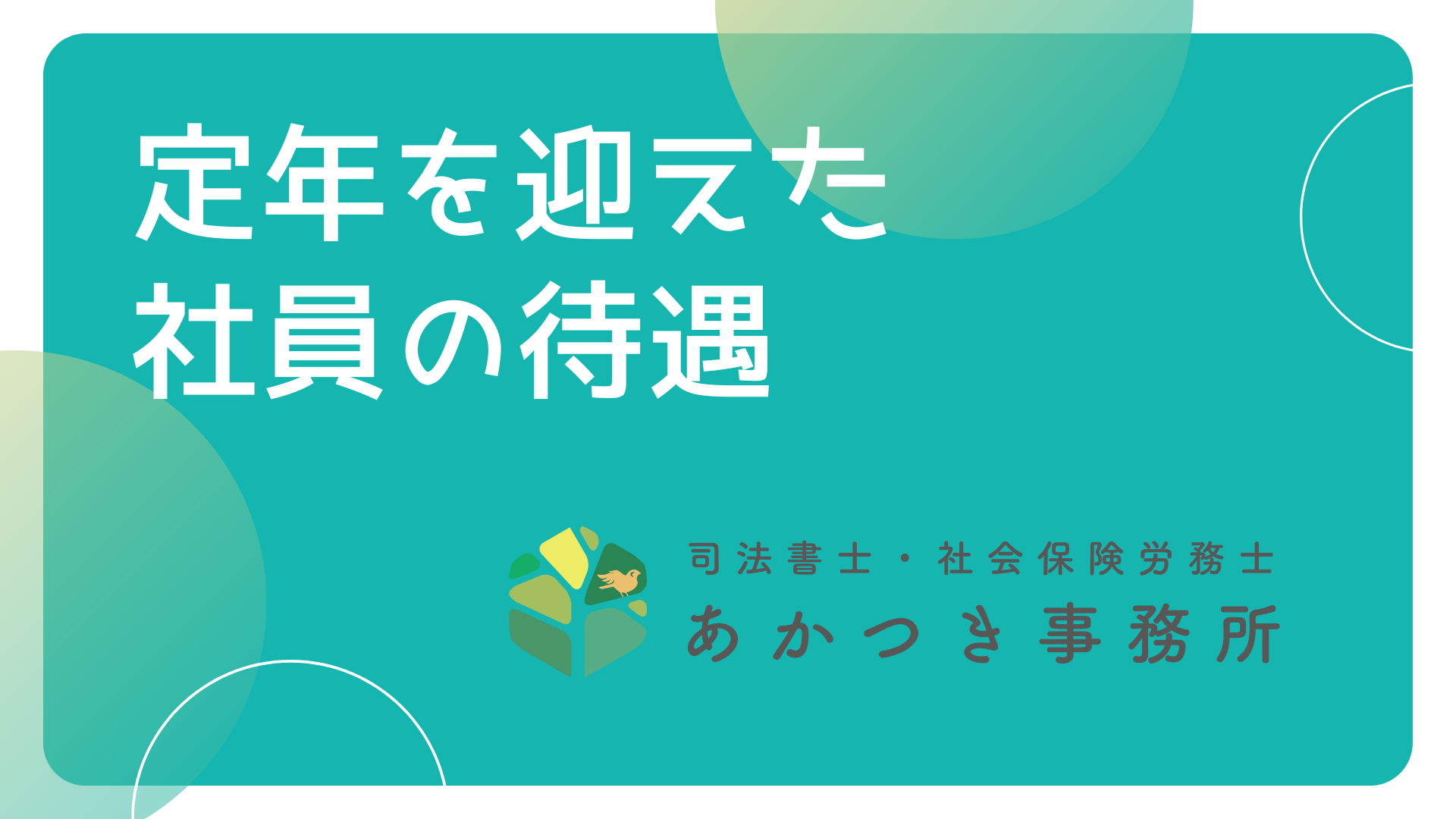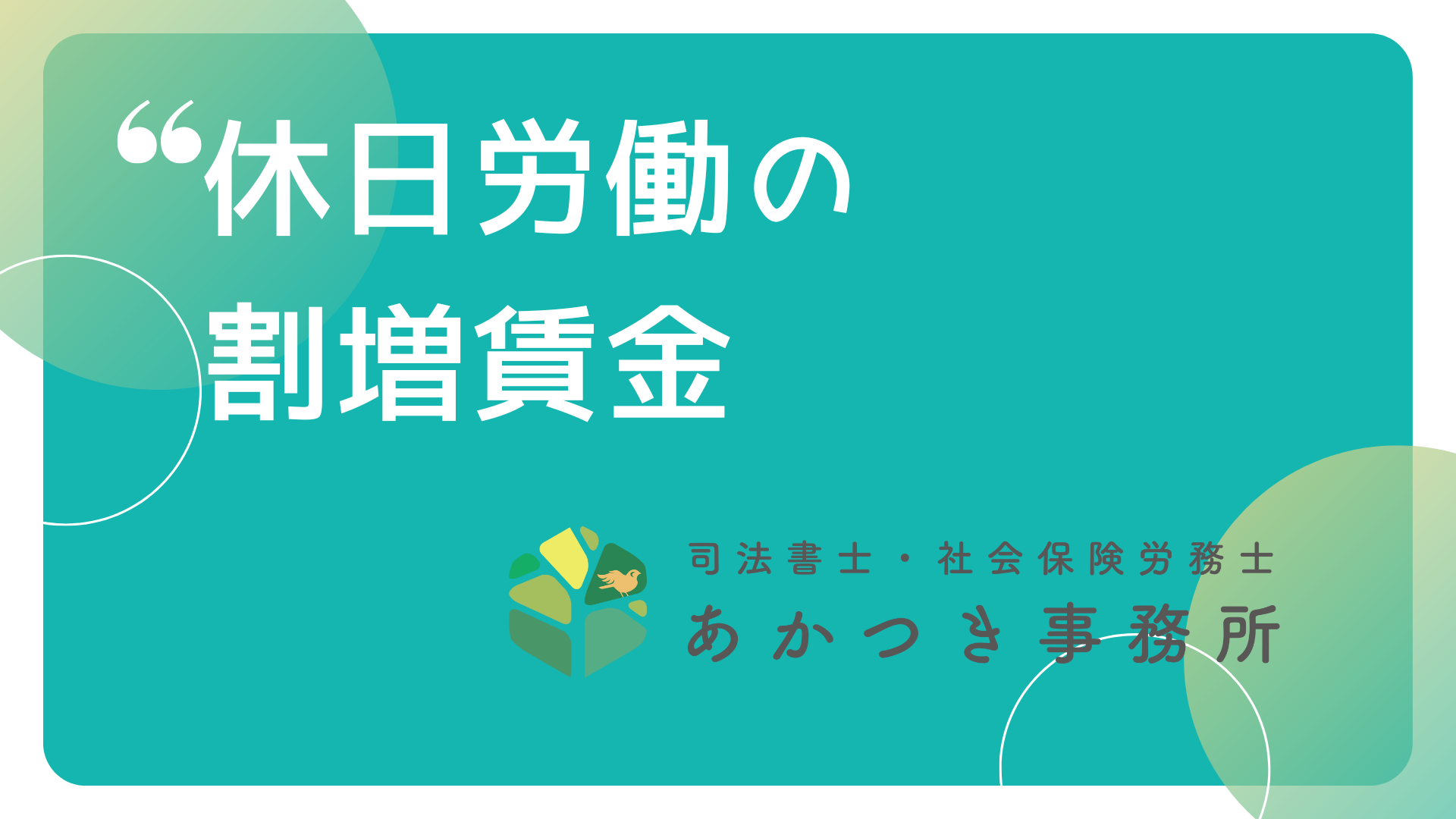1 正社員への転換の推進
日本の労働人口に占める非正規社員の割合は、約4割にも及びます。
そして、日本の正社員と非正規社員とでは待遇に大きな格差があり、社会問題にもなっています。
会社としても、正社員と非正規社員との間に不合理な待遇格差があることは、社員の勤労意欲の低下や離職率の増加につながり望ましい状態であるとは言えません。
そこで、待遇格差の是正のためのひとつの手段として非正規社員を「正社員に転換する制度」を設けることが有益であり、また、正社員化を推進することは、法律上の義務でもあります。
1-1 正社員への転換を推進するための措置
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下、「パート有期法」という。)第13条では、事業主に対し、非正規社員を正社員化するため下記のいずれかの措置を講じる義務を課しています。
・ 正社員の求人をする際に、その求人内容を、職場の非正規社員にも周知すること
・ 社内公募等に対する応募機会を非正規社員にも与えること
・ 一定の資格のある短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けること(正社員登用制度)
ただし、正社員登用制度を設けていたとしても、実際に運用していなかったり、正社員になるための要件が非常に厳しく正社員に登用実績がいような場合は、正社員登用制度を設けいているとは評価されない可能性がある点に注意してください。
なお、事業主は、非正規社員を雇用した際に、上記の措置の内容について説明する義務を負っています。(パート有期法第14条)
1-2 非正規社員の正規社員との待遇差を支えることに
パート有期法第8条では、非正規社員と正社員との待遇差の相違が不合理なものであってはならないと定めています。(いわゆる「同一労働同一賃金」です。)
その待遇差の相違が不合理であるか否かを判断する要素として、①職務の内容②人材活用の仕組み③その他の事情の3つがあります。
上記の「正社員登用制度」を設けていることは、③の「その他の事情」として考慮されることになります。
したがって、正社員登用制度は、賃金などの正社員と非正規社員の待遇に相違が認められる一つの要素となるので、積極的に取り入れていくとよいでしょう。
ただし、前述したとおり、正社員登用制度があるものの、実際は運用していなかったり、正社員となるための条件が非常に厳しく登用実績がないような場合は、「その他の事情」として考慮されにくいので注意が必要です。
2 有期契約社員の無期転換ルール
正社員登用制度がない場合であっても、労働契約法第18条の定めにより、労働期間が通算して5年を超える有期契約社員には、無期雇用契約に転換することを申込む権利(無期転換申込権)が発生します。この無期転換申込権により申込みがなされた場合は、有期契約社員は無期契約社員となります。このような制度を無期転換ルールと呼びます。
2-1 通算契約期間が5年を超えると
前述のとおり、有期契約社員の雇用期間が通算して5年を超える場合は、無期転換申込権が発生します。
「通算」してとは、2つ以上の有期労働契約が必要という意味ですので、当初から1つの労働契約が5年を超えているような場合で、1回も更新がないような有期契約社員については、無期転換申込権は発生しません。
また、無期転換ルールは、法律の施行日(2013年(平成25年)4月1日)以後に締結した有期労働契約が対象となりますので、施行日前に締結・更新のあった有期労働契約は通算しません。
さらに、1つの有期労働契約と次の有期労働契約の間に労働契約のない期間(空白期間)が6カ月以上ある場合は、その空白期間より前の有期労働契約期間は通算されません。この通算期間がリセットされることを「クーリング」といいます。
なお、契約期間が1年未満の有期労働契約の場合は、当該有期労働契約の雇用期間に2分の1を乗じて得た月数(1ヶ月未満の端数がある場合は、切り上げた月数)がクーリング期間となります。
2-2 無期契約社員になるのはいつからか
無期転換申込権については、通算して5年を超えることとなる労働契約の更新時に発生することになります。
(例:2年の有期労働契約の場合、2回目の更新が通算して5年を超える(計6年)になる労働契約の更新となるので、2回目の更新時に無期転換申込権が発生する。)
そして、無期転換申込権が発生した時から、当該無期転換申込権が発生した有期労働契約の期間が満了するまでの間に、申込みをすると、当該有期労働契約の期間満了をもって、無期契約社員に転換されることになります。
2-3 無期転換申込権が発生しない例外
雇用期間が通算して5年超える場合であっても、定年後に継続雇用した高齢者については、雇用管理に関する措置についての計画を厚生労働大臣に提出し、その認定を受けたときは、無期転換申込権が発生しません。(有期雇用特別措置法第8条第2項)
2-4 無期転換後の労働条件
無期転換後の社員の労働条件は、何の取決めもなければ契約期間に関する定めを除き、有期契約社員のときと同一の条件をそのまま引き継ぐことになります。
そうすると例えば、正社員には定年の定めがあるような場合であっても、無期転換後の社員については、定年の定めはなしとなり不都合が生じます。
このような不都合を回避するためにも就業規則などで無期転換後の社員の労働条件を定めておく必要があります。
なお、有期契約社員のときよりも労働条件を低下させることは、合理的な理由が必要であり、職務内容などに変更がないにも関わらず無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進める観点がらも望ましくないとされています。(平成24年8月10日基発810第2)
2-5 同一労働同一賃金との関係
非正規社員と正社員との待遇差の相違が不合理なものであってはならないと定めているパート有期法第8条の規定は、「短時間労働者」と「有期雇用労働者」を保護の対象としているため、そのいずれにも該当しない「無期転換したフルタイム社員」は保護の対象にはなりません。(無期転換した社員が短時間労働者の場合は、保護の対象です。)
したがって、正社員の労働条件と比べて、無期転換後のフルタイム社員の労働条件に不合理な相違があったとしても法律上、問題はありません。
しかし、「無期転換したフルタイム社員」と「無期転換前の有期契約社員」「短時間労働者」との間には、パート有期法第8条の規定が適用されるので、注意が必要です。
例えば、無期転換した際に労働条件を変更して、新たに手当をつけたような場合、両者の間で待遇差が生じることになります。
このような場合には、その待遇差が合理的なものであることを要求されるのです。
投稿者プロフィール

-
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。
1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。
最新の投稿
 労務・法務ニュース2024年3月29日令和6年4月1日から労働条件通知書の記載内容が変わります!
労務・法務ニュース2024年3月29日令和6年4月1日から労働条件通知書の記載内容が変わります! 労務・法務ニュース2024年2月17日「運送業」、「建設業」、「医師」の時間外労働の上限規制の適用について
労務・法務ニュース2024年2月17日「運送業」、「建設業」、「医師」の時間外労働の上限規制の適用について 労務・法務ニュース2024年2月7日令和6年3月の健康保険料率改定のお知らせ
労務・法務ニュース2024年2月7日令和6年3月の健康保険料率改定のお知らせ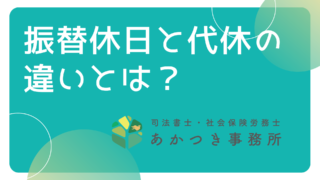 労働時間・残業・休日労働2024年1月16日振替休日と代休の違いとは?
労働時間・残業・休日労働2024年1月16日振替休日と代休の違いとは?