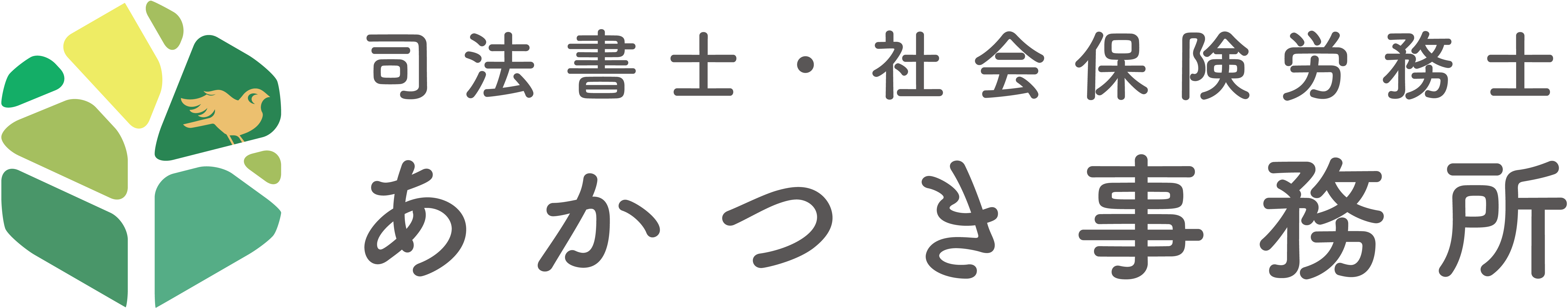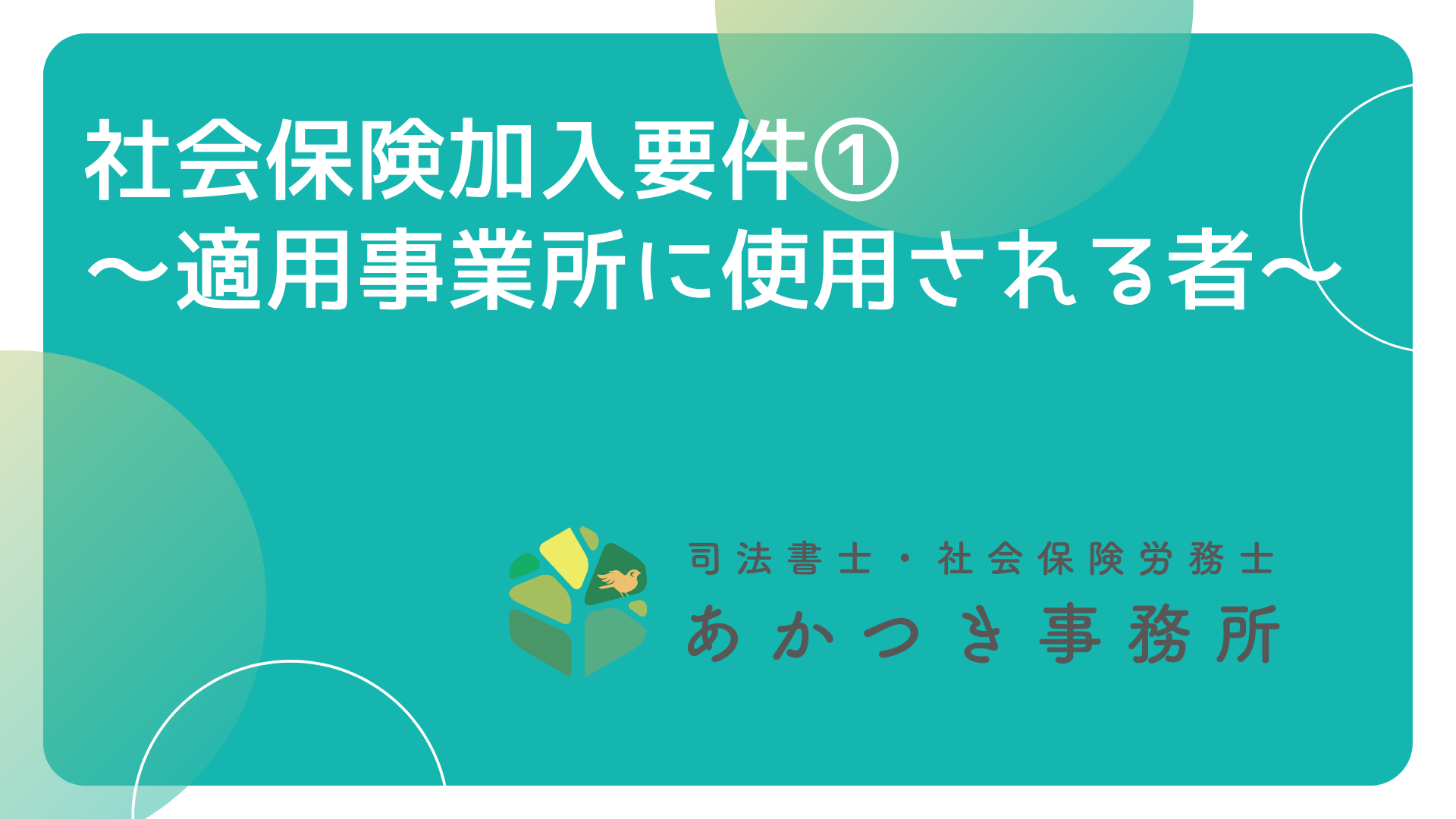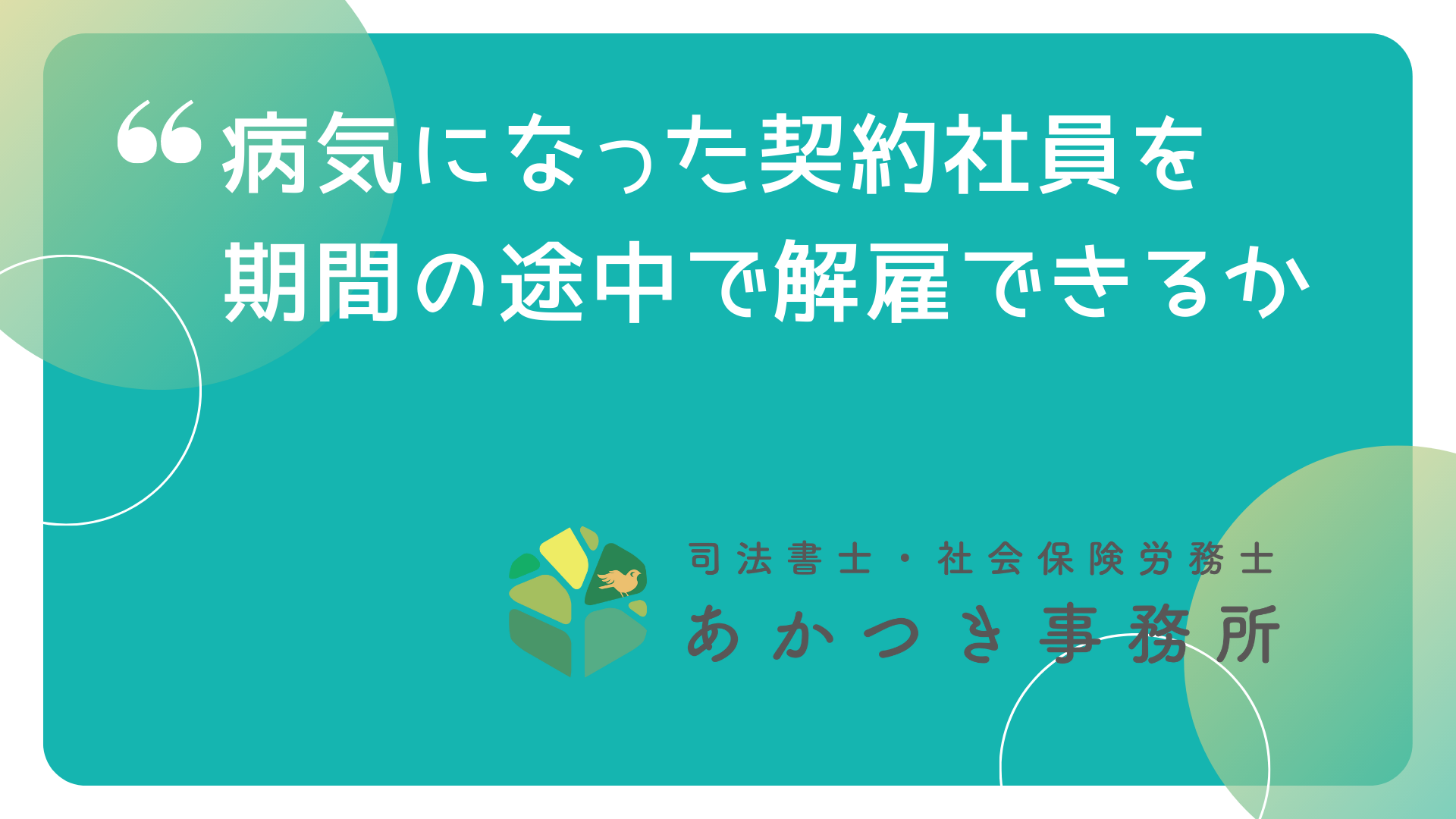皆様、こんにちは。社会保険労務士の出口勇介です。
今回は、社会保険加入に加入する要件のひとつである「4分の3基準」について解説します。
1 社会保険加入の要件
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する(被保険者となる)義務がある者とは、「適用事業所に使用される者」です。
「適用事業所に使用される者」とは、①法人の役員(一定の要件あり) ②通常の労働者(正社員) ③1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の者と比べて4分の3以上であるものが該当します。(4分の3基準)
※ 「適用事業所」については、前回の記事をご確認ください。
今回は短時間労働者の社会保険加入義務の基準である②の「4分の3基準」について詳しく見ていきます。
4分の3基準
1)「1週間の所定労働時間及び1か月の労働日数」の取扱い
就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週及び月に勤務すべきこととされている時間及び日数をいいます。
※「通常の週」とは、振替休日・国民の祝日・夏季休暇・年末年始休暇等が含まれる週以外の週をいいます。
2)「通常の労働者と比べて4分の3以上であるもの」とは
通常の労働者とは、正社員のことをいいます。
したがって、正社員と比べて「1週間の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が正社員と比べて4分の3以上ある短時間労働者についても社会保険の加入義務があることになります。
【4分の3以上の具体例】
正社員の1週間の所定労働時間が40時間の場合 ⇒ 週30時間以上の所定労働時間
正社員の1か月の所定労働日数が20日の場合 ⇒ 月15日以上の所定労働日数
2 実際の労働時間と乖離がある場合
1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数が正社員の4分の3未満の契約で雇用されたとしても、残業などにより常態として実際の労働時間及び労働日数が正社員の4分の3以上となっている場合どのように扱えばよいでしょうか。
こような場合、下記の基準を満たすのであるならば、当該労働者についても社会保険の加入義務があります。
4分の3以上が常態化している場合の取扱い
実際の労働時間又は労働日数が直近2か月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間又は当該所定労働日数は4分の3基準を満たしているものとして取り扱うこととするとされています。
したがって、4分の3基準を2か月連続で満たし、今後も4分の3未満になることはないと見込まれる者については、3か月目に社会保険に加入する義務が発生します。
なお、日本年金機構が上記加入義務を判断する際に所定労働時間又は所定労働日数が、就業規則、雇用契約書等から明示的に確認できない場合は、実際の労働時間又は労働日数を事業主等から事情を聴取した上で、個別に判断することとなります。
3 4分の3基準を満たさない短時間労働者の加入義務
4分の3基準を満たさない短時間労働者であっても、下記の5つの要件を満たす場合は、社会保険に加入しなければなりません。
5要件
① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 雇用期間が2か月を超えて見込まれること
④ 学生でないこと
3-1 賃金額8万8000円以上の判定方法とは
③の要件「賃金の月額が8万8000円以上であること」を判定するうえで、計算に含まれる賃金とは、基本給と諸手当の合算した額をいいます。
基本給が時給の場合は、時給額 × 週の所定労働日数 × 52週 ÷ 12カ月 で賃金の月額を求めます。
なお、諸手当についても合算しますが、下記の賃金は8万8000円以上かを判定するうえでの賃金からは除外されます。
8万8000円以上かを判定するための賃金から除外されもの
① 臨時に支払われる賃金
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 時間外労働に対する割増賃金(時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当)
④ 最低賃金に算入しないことが定められている賃金(精勤手当、皆勤手当、家族手当)
※注意すべきは、年収が130万円未満であっても、月額8万8000円以上であり、自らが被保険者となった場合は扶養から外れることになります。
3-2 「特定適用事業所」、「任意特定適用事業所」とは
「特定適用事業所」とは、事業主が同一である1または2以上の適用事業所で、1年のうち6カ月以上、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時101人以上の事業所となることが見込まれている企業等をいいます。
※「被保険者数の総数が常時101人以上」の判定は、労働者の数ではなく、社会保険の被保険者の数で判断します。
「任意特定適用事業所」とは、国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所をいいます
【令和6年10月の改正】
・特定事業所の要件である「被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所」が「被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時51人以上事業所」に変更されます。
4 社会保険加入手続を怠ったら
4-1事業主について
社会保険の加入義務があるにもかかわらず加入義務を怠った場合、事業主には、下記の不利益があります。
・ 過去2年間に遡って保険料が徴収される
・ 罰則として、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる
・ 労働者が本来もらえる年金がもらえなかったことにより損害賠償請求される
・ 建設業の場合は建設業の許可がとれない
4-2労働者について
社会保険の加入義務があるにもかかわらず事業主が加入手続をしない場合、労働者は、日本年金機構へ資格の確認請求をすることができます。(加入義務が確認されたら過去2年分にさかのぼって保険料が徴収されます。)
5 まとめ
いかがでしたでしょうか。
社会保険の加入は法定の義務のため要件を満たした労働者は必ず社会保険に加入しなければなりません。
社会保険の加入手続にお困りの方は、社会保険労務士あかつき事務所までご連絡ください。
お気軽にお問い合わせください。042-649-4631「ホームページを見た」とお電話ください営業時間 9:00 – 18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ投稿者プロフィール

-
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。
1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。
最新の投稿
 労務・法務ニュース2024年3月29日令和6年4月1日から労働条件通知書の記載内容が変わります!
労務・法務ニュース2024年3月29日令和6年4月1日から労働条件通知書の記載内容が変わります! 労務・法務ニュース2024年2月17日「運送業」、「建設業」、「医師」の時間外労働の上限規制の適用について
労務・法務ニュース2024年2月17日「運送業」、「建設業」、「医師」の時間外労働の上限規制の適用について 労務・法務ニュース2024年2月7日令和6年3月の健康保険料率改定のお知らせ
労務・法務ニュース2024年2月7日令和6年3月の健康保険料率改定のお知らせ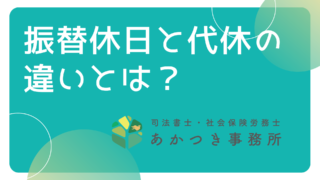 労働時間・残業・休日労働2024年1月16日振替休日と代休の違いとは?
労働時間・残業・休日労働2024年1月16日振替休日と代休の違いとは?