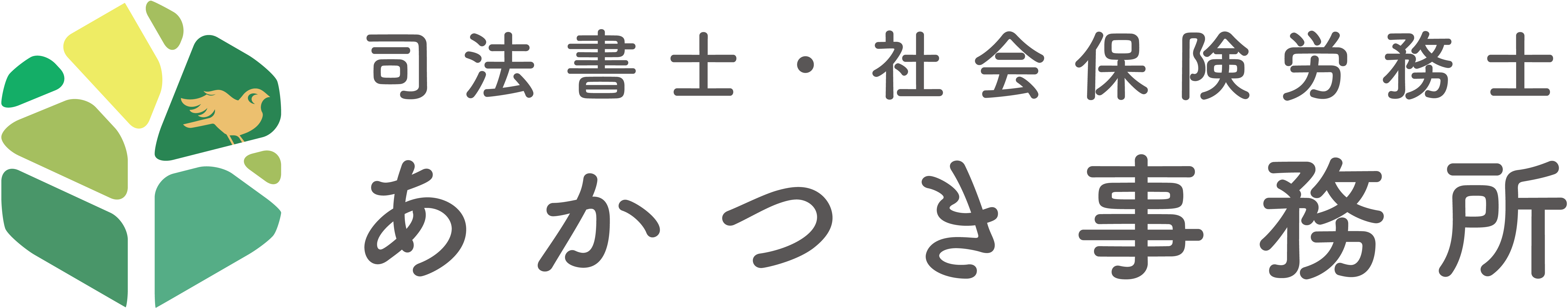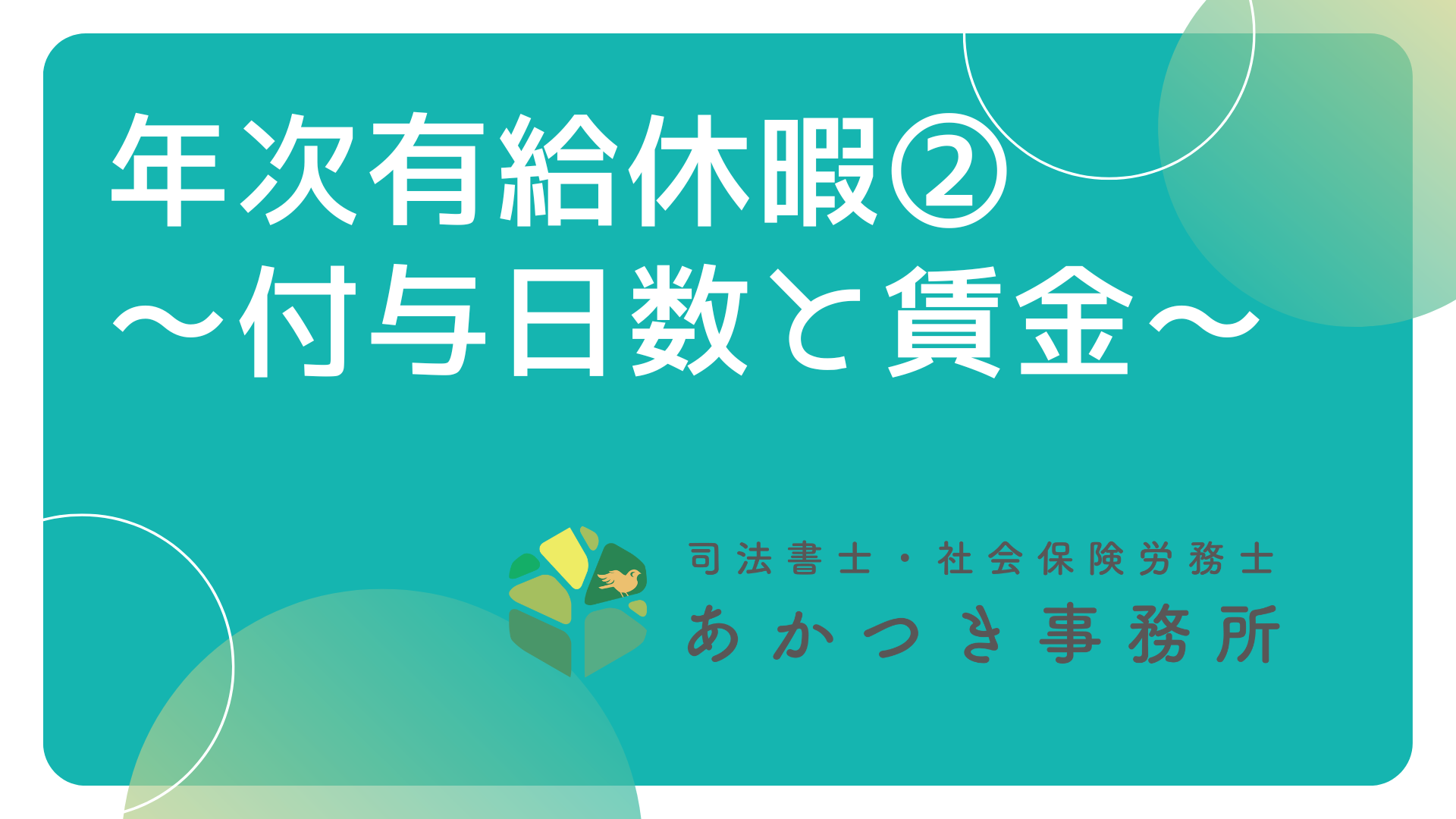1 年次有給休暇とは
「年次有給休暇」とは、使用者が、労働者に賃金を支払いながら労働日における労働の義務を免除する(休暇を与える)制度のことです。
企業側のメリット
労働者が年次有給休暇を取得すると、
① 休暇とることでリフレッシュし、効率的・創造的な働き(労働生産性の向上)を実現できる
② 業務を引き継がせる代替要員の多能化を促進する
③ 休暇を利用して労働者がキャリアアップを図ることができる
などといった、業務の効率化、人材の育成につながり、企業経営にも良い影響をもたらすことになります。
国としても、日本の経済成長・少子化対策などの理由に、年次有給休暇の取得を促進しています。
2 年次有給休暇の発生要件
年次有給休暇の権利は、下記の2つの要件を満たすことで発生します。(労働基準法第39条第1項)
① 一定期間の継続勤務
年次有給休暇の権利が発生するには、雇入れから6か月間、継続勤務をする必要があります。
その後は、継続勤務年数1年毎に、新たな年次有給休暇の権利が発生します。
なお、「継続勤務」とは、労働契約の存続期間(在籍期間)をいいます。(昭和63年3月14日基発150号等)
継続勤務として扱われるもの
下記の場合は、継続勤務として扱われ、その勤続年数が通算されます。
・ 定年後再雇用(再雇用まで相当期間がないこと)した場合
・ 臨時工、パート等を正社員に切り替えた場合
・ 休職者が復職した場合
・ 在籍出向した場合
など
② 全労働日の8割以上の出勤率
出勤率の計算の対象期間について、下記の計算式により算出した「出勤率」が8割以上であることが必要です。
出勤した日 ÷ 全労働日 = 出勤率
【 出勤率の計算の対象期間 】
・ 雇入れ日から6か月間
・ 雇入れ日から6か月経過した日以後は、1年間ずつ
※ なお、出勤した日に含める期間・日、及び全労働日から除外する日は下記のとおりです。
「出勤した日」に含める期間・日
・ 労働災害により休業した期間
・ 育児・介護休業期間
・ 年次有給休暇を取得した期間
・ 労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日
「全労働日」から除外する日
・ 不可抗力による休業日
・ 使用者側に起因する経営・管理上の障害による休業日
・ 正当なストライキその他正当な争議行為により労務の提供が全くされなかった日
・ 所定の休日に労働した日
・ 代替休暇を取得して終日勤務しなかった日
年次有給休暇の権利の発生については、上記の2要件を満たせば当然に発生するため、労働者の請求は不要です。
3 法的性質
使用者の承認は必要か?
労働者が年次有給休暇を「請求する」といった場合、それは単に休暇の時季を「指定する」ことを意味します。(時季指定権)
労働者が年次有給休暇を請求する、すなわち休暇の時季を指定する(時季指定権を行使する)と、その指定した日について年次有給休暇の効果(指定した日の労働義務の免除及び賃金支払請求権)が発生します。
これは、労働者が年次有給休暇を請求することに対し、使用者の承認を要しないことを意味します。
「指定」ではなく「請求」と解釈した場合の不都合
年次有給休暇の成立要件を、労働者による「休暇の請求 (=休暇の付与(使用者が労働義務の免除の意思表示をすること)の申込み) 」と解釈すると、これに対する使用者の「承認( =休暇付与の義務(労働義務を免除する意思表示をする義務)を履行すること )」が必要となります。(債権と債務の関係)
すると使用者がその承認をする義務を履行しないならば、労働者は、改めて年次有給休暇の承認を訴求するという迂遠な方法をとる必要がでてきます。
これでは、年次有給休暇の趣旨・目的に反し適切ではないため、この考え方は採用されていません。
(昭和48年3月2日白石営林署事件)
利用目的を制限できるか?
年次有給休暇の利用目的は、労働基準法が関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由とされています。 (白石営林署事件:昭和48年3月2日)
よって、就業規則などで、年次有給休暇の利用目的に制限を設けることはできません。
それでは、労働者が年次有給休暇を請求する際に、使用者がその利用目的を尋ねこともできないのでしょうか?
一般的には、その利用目的を尋ねることで、労働者が年次有給休暇に取得を躊躇することもありえますので控えたほうがよいでしょう。
ただし、使用者が時季変更権を行使する段階では、利用目的を尋ねることが認められる場合があります。(電電公社此花局事件:昭和57年3月18日)
使用者が、時季変更権を適法に行使するための要件である「事業の正常な運営を妨げる場合」の有無を判断するにあたっては、労働者の事情も考慮されるため、この労働者の事情を確認する範囲において利用目的を尋ねることができます。
投稿者プロフィール

-
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。
1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。
最新の投稿
 労務・法務ニュース2024年3月29日令和6年4月1日から労働条件通知書の記載内容が変わります!
労務・法務ニュース2024年3月29日令和6年4月1日から労働条件通知書の記載内容が変わります! 労務・法務ニュース2024年2月17日「運送業」、「建設業」、「医師」の時間外労働の上限規制の適用について
労務・法務ニュース2024年2月17日「運送業」、「建設業」、「医師」の時間外労働の上限規制の適用について 労務・法務ニュース2024年2月7日令和6年3月の健康保険料率改定のお知らせ
労務・法務ニュース2024年2月7日令和6年3月の健康保険料率改定のお知らせ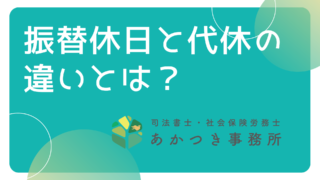 労働時間・残業・休日労働2024年1月16日振替休日と代休の違いとは?
労働時間・残業・休日労働2024年1月16日振替休日と代休の違いとは?